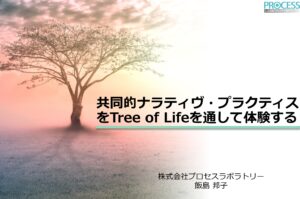ナラティヴ・アプローチって?
プロセスラボラトリーでは、ファシリテーションとナラティヴ・アプローチを事業の軸に据えています。ファシリテーションについては、以前こちらの記事で書いてみました。今日はナラティヴ・アプローチについて、改めて書いてみようと思います。
ナラティヴ・アプローチとは、他者との関りによって現実を作る言葉に意味がもたらされるという社会構成主義を前提にした、オーストラリア/ニュージーランドのソーシャルワーカー、マイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンの貢献によって形作られた対人支援の世界で発展してきたアイデアと実践です。対人支援の領域では、ナラティヴ・セラピーと表現しますが、哲学、文化人類学、社会学、民俗学などからの叡智を取り入れ、心理療法に限らず、関係の修復的実践、学校教育、組織/コミュニティでの実践など、多くの領域で活用されるようになっていることから、ナラティヴ・プラクティス、ナラティヴ・アプローチとも呼ばれています。
言葉が現実をつくりだす社会構成主義を基盤としていることを考えると、端的に表現することを少し躊躇してしまうのですが、現時点での個人的な整理を言葉にしてみるとするならば、「人に敬意を示し、その人の人生の物語に影響を及ぼしている社会文化的背景との関係に着目する対話実践」ということができるでしょう。
人々は出来事を理解する時にストーリーとして理解し、ストーリーに織り込まれた意味が人々の経験を形づくる。そしてストーリー上の人々の思考や信念は絶えず文化的環境の影響を受けていると考えます。その文化的環境からの影響を受けた当然のこととする信念は、時に人々の人生を支配してしまうことがあります。この当然のこととする信念からの影響を捉え易くするために、マイケル・ホワイトたちは、「人も人間関係も問題ではない。むしろ問題が問題である」という眼差しと、外在化しながら再著述する会話のあり方を生み出しました。
ナラティヴの実践では、人々の人生の物語を支配してしまう物語のことを「ドミナント・ストーリー」と表現します。ナラティヴ・アプローチとは、その「ドミナント・ストーリー」を対話を通して緩めていく実践であり、他者と共に語り直すことで「オルタナティヴ・ストーリー」として編み直していく、つまり再著述していくプロセスといえます。誰もが自分の人生の物語の著者として、その物語を語り直し、書き直し続けられる。つまり、再著述とは、既にある物語を書き替えるという静的な営みではなく、自らの物語を語り直し続けるという動的な概念であり、自己は、他者との対話や関係性のなかで形づくられ、動きうるものと考える社会構成主義とつながる、ナラティヴ・アプローチの中核をなす実践です。
弊社では、「コミュニティ(Community)」も同様に、物理的で静的な集団というより、相互に関係し合う人々の間に生まれる質的つながりであり、流動的な概念と捉えるならば、グループや組織の物語も再著述することができると考え、このナラティヴ・アプローチの眼差しとあり方を、対話型組織開発の取り組みに取り入れています。
もし、ご自身のコミュニティ(組織、チーム、地域)の関係の物語に何かしらのアプローチをお探しならば、ぜひ一度お問い合わせください>こちらまで